今回の記事ではチェコの小説家 フランツ・カフカを紹介します。
カフカは20世紀を代表する作家と言われますが、写真を見るといわゆる文豪らしい見た目とはかけ離れた、繊細そうな青年が写っています。

1883年にプラハで生まれ、厳格で屈強な父にコンプレックスを抱きながら成長したカフカは、役所勤めをしながら執筆活動を行いました。40歳の若さでこの世を去るまで、その名が広く知られることはなかったといいます。
死後にその評価が高まりましたが、生前の彼は生活のために働きながらコツコツと自身の内面を吐き出すように書き続けた、サラリーマン作家だったのです。
カフカの作品は実在主義の文脈で語られ、分析されることが多いですが、おそらく本人はそんな意識はなく、ただ自身の内面からあふれ出る言葉を物語や手紙にして書き留めていたにすぎないのではないでしょうか。
家族に対して、恋人に対して、仕事に対して、社会に対して、自分に対して、そしてその人生に対して、誰しもが共感し得る極めてパーソナルな内面の思考を寓話的に物語にしたにすぎず、だからこそ世界中で多くの読者を獲得するに至ったのだと思います。
この記事では、そんなカフカの内面が投影された作品を短編2作、中編1作、長編1作ピックアップして紹介します。
父への愛憎と「判決」

遠くロシアに住む友人へ、自身の婚約を知らせる手紙を書く男。父親にそれを報告しようと、ふと部屋を訪ねたことで、父親の口から現実とも虚構とも判別できない言葉の数々を聞くことになり、困惑の中、溺れ死ねと宣告される。男は家を飛び出し、橋の上から身を投げるのだった。
1912年、カフカが29歳の時に書き上げた短編小説「判決」。前半では、主人公の男は友人に対しても、父親に対しても、哀れみや同情に近いような視線を向け、気を使い、手を差し伸べるような態度をとります。しかし後半では一転、父親が主人公の男を掌の上で転がしていたかのような発言をすると、男は動揺し、物語は混沌としていきます。
この男は、父親を愛しているようにも、憎んでいるようにも感じられません。まるで得体の知れない、自分とは相いれない生き物かのように扱っている印象を受けます。ただし、その影響は強力で、自身の運命を左右する力を持っている存在であることが、結末からは感じられます。
カフカは36歳の時、つまり死去する数年前に、数十ページにも渡る長い手紙を父親宛に書いています。これは父親が目にする前に母親が読んだことで、結局父の手に渡ることはなかったそうです。この手紙の中には、母が隠すのも納得するような父に対する恨み言で埋め尽くされています。幸いにも後世の私たちはそれを読むことで、カフカが父親に対して抱いていた感情を知ることができます。
そこには、幼少期に水をねだっただけで下着姿のままバルコニーに放り出された理不尽な経験がトラウマとして残り、父にとって自分はそれだけ無価値な人間なのだという考えにとらわれていたこと。父親の独善的な態度が自分の自信を奪い、未来の可能性を狭めていったこと。自分に対する母親の優しさも、結局は父親の為であると感じていたこと。など、赤裸々につづられています。
これらを読んだ上で、再度「判決」の物語に視線を戻すと、父親の支離滅裂で理不尽な発言の数々、そしてそれらが帯びている妙な恐怖と謎の説得力と支配力は、カフカが実際に感じていた「印象」をそのまま写し出したものなのかもしれません。そこに論理的なストーリー展開や、動機付けは不要なのです。なぜならそれらは、実際に(少なくともカフカにとっては)、起こってきた事実なのですから。
この作品は後にカフカの婚約者となる女性フェリーツェ・バウアーと出会って間もない頃に、一晩で書き上げられたそうです。物語の中には、主人公の婚約に対して否定的な父親の発言が出てきます。カフカの彼女に対して向かおうとする想いにも、父親の影響が暗い影を落とし、作品へのインスピレーションとなっていたのかもしれません。
作家としての誇りと「断食芸人」
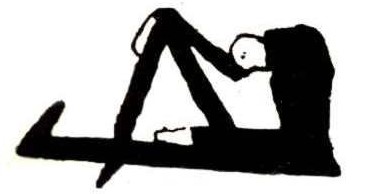
何日も断食を続ける行為をサーカスの見世物とする断食芸人。人々はどうせつまみ食いをしているのだろうと疑るが、そうして目を光らせて見張られることは芸人にとって心地よく、気を使って「つまみ食いをどうぞ」とばかりに目を離される方がむしろ誇りを傷つけられた思いがするのだった。注目を集めた日々が去り、人々に忘れ去られてからも芸人は断食を続け、やがて息絶えた。葬られた芸人に代わって、檻には生命力溢れる一匹の豹が入れられたのだった。
1922年、晩年に発表された短編「断食芸人」は作家としての成功を志しながらも、大きな成果を上げられないまま、サラリーマン作家として生きたカフカが自身の生涯を投影したような物語です。
彼は日記に、文学こそが自分の使命であり、唯一やりたいことだと書き残しています。しかしながら、作家として生計を立てる自信はなく、病気で退職することになるまで勤めを続けました。
自分は作家であるという誇りと、生活の為にサラリーマンを「つまみ食い」している現実の自分。このジレンマはカフカにとって耐えがたいものであったことが想像できます。
気を使われることで、かえって誇りを傷つけられる思いがする。
これは苦行ではなく、いつまでも続けられるのに、なぜ人に中断させられなければならないのか。
人気者の隣に置かれるのは不愉快である一方で、その恩恵を受けている事実がある。
苦しい道を自ら選んでいるのは、感心されるようなことではなく、そうするしかなかっただけのこと。
こうした断食芸人の感情や思考は、創作活動の中でカフカが抱いていた思いがそのまま反映されているように感じます。
芸の道に一途にその身を捧げた断食芸人の生き方は、カフカにとって、表現者として理想の姿であったのかもしれません。
不確かな存在と「変身」

ある朝、目がさめると虫になっていた男グレーゴル。なぜ虫になったのか、その理由は分からないまま、そしてグレーゴル自身もそれを不思議には思わないまま、物語は進みます。初めは世話をし、哀れんでいた家族は、次第に彼を疎ましく思うようになっていきます。
1912年に書かれ、カフカの小説でもっとも有名な作品となった「変身」は、奇怪でありながら、ユーモアと悲しみに満ちた名作です。
設定だけ聞けばファンタジー、虫の描写を読めばグロテスクなホラーですが、100ページ足らずの中で描かれる一家の心情の変化は実に身につまされるもので、家族の中の人間関係を巧みに描いたドラマとして非常に読み応えがあります。
異常な状況なのに仕事に行く時間を気にするグレーゴル、変わり果てた姿の息子に対して見て見ぬ振りをする両親、そして特筆すべきはけなげに世話をする妹です。はじめはその役割を一手に引き受け、熱心に兄の面倒を見ていた妹が、次第にぞんざいな扱いを始め、その巨大な虫をやっかいものとして感じるようになるのです。
虫に変身する、という特異なものでなく、例えばこれが突然の病気や交通事故で寝たきりになったものだとしたら?あるいは、仕事を失って家に引きこもるようになったのだとしたら?果たして家族は、自分のために身を砕いて尽くしてくれるだろうか?また、自分は尽くせるだろうか?
何かしらのハンディを背負った家族のために、自分の人生を捧げるような美談は物語として美しく、感動的なものでしょう。しかしこの物語の中にそんな家族関係は登場しません。ゾッとするほど晴れやかなラストシーンは、強烈な皮肉となって胸に突き刺さります。
根源的なコミュニティである家族の中で、自分の存在にはいったいどれだけの価値があるのか。それはそのまま、自分自身で自覚できる、根源的な価値になります。家族にとって自分は、かけがえのない存在なのか。カフカにとってのそれは、とても不確かなものだったのかもしれません。
満たされない想いと「城」

測量士であるKは、城から仕事の依頼を受け、雪深い村へとやって来るが、なかなか城へたどり着くことができない。次々と現れる村人たちとのコミュニケーションはどこか噛み合わず、思うように物事が進まないまま、時間だけが過ぎていく。
カフカにとって最晩年に当たる1922年から書き始められた未完の長編です。
村人たちが何かを隠すために、わざとKを城から遠ざけているのか?というミステリアスな雰囲気で物語は進みますが、読み進めるうちにK自身すら本心では城から遠ざかろうとしているのでは?と感じるようになります。そして最終的には書き手すら信用できなくなってきたころに、どこにも終着しないまま、突然物語は終わります。
あらゆる目的は果たされず、想いは実らず、不意に終わりを迎える物語。これは満ち足りることのなかったカフカの人生そのものに感じられます。
家族との関係も、恋人への想いも、作家としての自尊心も、何一つ満たされておらず、また、いつかは満たされるのかもわからないまま、誰が何のために必要とするのかもわからない事に時間を割かれて日々が過ぎていく。そこに焦りは間違いなく感じているものの、何となく居心地の良さも感じている自分がいる。その事実に罪悪感は増していく。
これは、そんなカフカの心情を追体験する物語なのかもしれません。だからこそ、「城」はカフカの集大成として、なるべくして未完となったのではないでしょうか。
いかがでしたか?
今回の記事では、チェコの作家 フランツ・カフカを紹介しました。
次回の記事では、カフカの作品の中からおすすめの作品をピックアップしてレビューしていきます。



コメント