今回の記事では、以前ご紹介したチェコのシュールレアリスト ヤン・シュヴァンクマイエルの作品を追加で紹介します。
今回はそこで紹介しきれなかったおすすめ作品を時系列順でレビューしていきます。

シュヴァルツェヴァルト氏とエドガル氏の最後のトリック 1964年/12分

シュヴァンクマイエルの映画監督としてのデビュー作は、意外にも生身の人間が登場する仮面劇でした。
デビュー作にはその作家のエッセンスが詰まっていると言われますが、たしかに今作には、役者も人形も小道具もアニメも全ては自分の脳内イメージを具現化するためのツールにすぎないと思っていそうな演出態度はすでに確立されています。
オープニングから曲をぶつ切りにし、人に不快感を与える天性のセンス、偏執的に繰り返す構成、それら「シュヴァンクマイエル的」な要素があちこちにあふれています。
評価☆☆☆
J.S.バッハ-G線上の幻想 1965年/10分
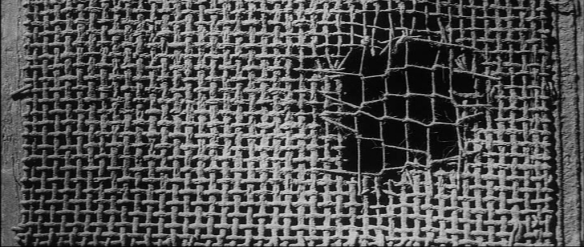
男が建物の中に入って行くシリアスなオープニングは、これからハードボイルドなノワールが始まるのかと思わせます。
しかしそこから展開されるのはバッハの楽曲に乗せた映像のコラージュでした。
意味ありげな映像が続きますが、その意味を探るよりも、意思を持ったように動くカメラと音楽との調和に身を委ねれば良い作品だと思います。
監督二作目とあって、コラージュの独創性はまだ薄めで、物足りなく感じてしまいました。
評価☆★
石のゲーム 1965年/8分

時が来ると蛇口が石を絞り出し、石たちは音楽に合わせてダンスするように動き回る。
モノトーンの美しさに見とれ、オルゴールの音色に聞き惚れていると突然訪れるパターンの崩壊と静寂。
永遠に続きそうな規則性とその唐突な瓦解を描く展開は、社会主義国家の閉塞感と解放への渇望を表現する上でのシュヴァンクマイエルの十八番となりました。
石で作ったアルチンボルド風の人物が登場したり、互いに喰らい合う展開は後の傑作「対話の可能性」を予感させます。
評価☆☆☆
ヴァイスマンとのピクニック 1968年/11分

普段は部屋から出ることのない蓄音器やクローゼットが、野原でピクニックを楽しみます。
その様子は生き生きとしており、生の喜びを謳歌しているかのようです。
やがて季節が過ぎて落ち葉が降り積もると、衣替えでもするように、人間はクローゼットからお払い箱になります。
人と物の境界が曖昧なシュヴァンクマイエルらしい作品です。
評価☆☆☆
ジャバウォッキー 1971年/14分

子どものとりとめのない妄想をそのまま映像化したような作品。
かわいらしさの中からヒヤッとする恐ろしさが現れる感じ。秩序がないようであり、あるようでない感じ。まさにシュールレアリストの真骨頂です。
また猫にやられると分かっていても迷路を目で追ってしまうあたり、完全にシュヴァンクマイエルの術中にはまっている気がします。
評価☆☆☆★
肉片の恋 1989年/1分

2枚の肉片がじゃれ合い、愛し合い、焼かれるだけの1分間に、食べ物への嫌悪感や性的衝動、ブラックユーモアといったシュヴァンクマイエルらしいエッセンスが感じられる短編。
ラストのあっけなさと容赦のなさが素晴らしいです。
評価☆☆★
フローラ 1989年/1分

野菜でできた人間がベッドに横たわり、急速に朽ち果てていく映像。
メッセージを感じられなくても、そのダークでどこかグロテスクなビジュアルはインパクト抜群です。
評価☆☆
スターリン主義の死 1990年/10分

社会主義国家に対して批判的な作品を作り、検閲を受けてきたシュヴァンクマイエルですが、共産党政権が倒れたことで直接的な表現で政治的な作品を作ることが可能になりました。
しかし創作上の自由が必ずしも良い影響をもたらすとは限らず、今作では主張に意識が向きすぎたためか映像のコラージュは凡庸で、直接的な割には結末が曖昧な物足りなさが残る作品となっています。
評価☆☆
ファウスト 1994年/97分

シュヴァンクマイエルの二作目の長編は、人間の飽くなき欲望という実に彼らしいテーマを扱ったファウスト伝説を自己流に解釈した、実写と人形劇とが入りまじった作品です。
論理を超えた展開は正にシュールレアリズム的で、無意識下での思考の流れに身をゆだねる心地良さがあります。
しかし前作の「アリス」はストーリー自体が脱線の連続であったのに対し、こちらは真っ当なストーリーがベースとなっているためか脱線が控えめで、振り切れていない印象を受けました。
代名詞であるグロテスクで生理的嫌悪感を引き起こすような描写も控えめで、物足りなさを感じます。
とはいえ、人形劇のコミカルさからダークなオチまで見どころの多い作品ではあります。
評価☆☆☆
ルナシー 2005年/123分

ポーとサドからの引用をしながらも、まぎれもないオリジナリティが発揮された精神的ホラー映画。
人間が築く社会組織はそれが自由主義であれ、管理主義であれ不完全なもので、人間が自由であるためには、結局は個人として抗い続けるしかないのだというメッセージは、社会主義国家で創作を続けてきたシュヴァンクマイエルらしいテーマではあります。
善も悪も、食欲も性欲も、美徳も背徳も、全てがない混ぜになった狂気の世界は常軌を逸しており、嫌悪感を引き起こすのにどこか魅力的です。
シーンの合間に挿入されるストップモーションの悪夢的イメージには既視感が否めず、過去の短編の焼き直しという印象。
意外にもストーリーがしっかりしているので、つなぎはなくても良かった気がします。
評価☆☆☆☆
さいごに
いかがでしたか?
今回の記事では、デビュー作を含めた8本の短編と2本の長編をご紹介しました。
次回の記事でも、引き続きシュヴァンクマイエルの作品をレビューしていきます。



コメント